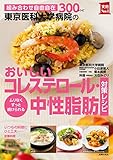脂質代謝異常の症状
脂質代謝異常の無症状期における診断の重要性
脂質代謝異常症は基本的に無症状で進行する疾患であり、初期段階では特に自覚症状が現れることはありません。このため、多くの患者は健康診断や定期的な血液検査によって偶然発見されるケースが大半を占めています。無症状であっても体内では動脈硬化が静かに進行しており、放置すると重篤な心血管疾患を引き起こす危険性があるため、早期発見が極めて重要となります。
参考)脂質異常症徹底ガイド:症状、原因、種類、疫学をわかりやすく解…
血液中の脂質濃度が高値でも、通常は身体的な不快感や痛みなどの症状を伴わないため、患者自身が異常に気づくことは困難です。このことが脂質代謝異常症を「サイレントキラー」と呼ばれる所以であり、医療従事者として定期的なスクリーニングの重要性を患者に啓発する必要があります。
参考)脂質異常症 - 12. ホルモンと代謝の病気 - MSDマニ…
脂質代謝異常における黄色腫の臨床的意義
血液中の脂質濃度が特に高い場合、脂肪が皮膚や腱に蓄積して黄色腫と呼ばれる特徴的な病変を形成することがあります。黄色腫は、マクロファージと呼ばれる免疫細胞の中に多くの脂肪が入り込み、それが皮膚に集まることで生じる黄色から橙色の斑状、丘疹状、または結節状の病変として観察されます。
参考)https://medicalnote.jp/diseases/%E9%BB%84%E8%89%B2%E8%85%AB%E7%97%87
眼瞼黄色腫はまぶたに好発し、左右対称性に出現することが多く、進行すると下眼瞼にまで広がることがあります。アキレス腱黄色腫は家族性高コレステロール血症の診断において重要な所見であり、腱の肥厚として触知されます。手の関節周辺、肘頭部、膝蓋部なども機械的刺激を受けやすい部位として黄色腫が生じやすい場所です。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6099072/
黄色腫自体は良性病変であり、通常は痛みやかゆみといった自覚症状を伴いませんが、その存在は全身の脂質代謝異常を反映しており、動脈硬化性疾患の高リスク状態を示唆する重要な臨床マーカーとなります。約半数の症例で高コレステロール血症や高トリグリセリド血症などの脂質異常症を合併していることが知られています。
参考)眼瞼黄色腫を治療するなら
脂質代謝異常が引き起こす動脈硬化のメカニズム
脂質代謝異常による最も重大な病態は動脈硬化の進行です。血液中のLDLコレステロールが過剰になると、血管の内皮細胞の隙間から血管壁に侵入し、そこで酸化されることで炎症反応を引き起こします。この過程でマクロファージが酸化LDLコレステロールを取り込み、泡沫細胞となって血管壁に蓄積し、ドロドロした塊であるプラークを形成します。
参考)脂質異常を改善する生活術|けんぽだよりWeb
プラークの形成により血管内腔が狭窄し、血液の流れが阻害されるだけでなく、プラークの表面が破綻すると血栓が形成され、血管を完全に閉塞させる危険性があります。中性脂肪が増えすぎると、HDLコレステロールの減少と小型化したLDLコレステロール(超悪玉コレステロール)の増加を招き、この小型LDLは血管壁に入り込みやすいため、動脈硬化のリスクが一段と高まります。
動脈硬化の進行は全身の臓器に影響を及ぼし、冠動脈が障害されれば心筋梗塞、脳血管が障害されれば脳卒中、下肢の血管が障害されれば閉塞性動脈硬化症といった重篤な合併症を引き起こします。特に脂質異常症と高血圧が合併している場合、動脈硬化の進行速度が加速し、合併症の発症リスクが相乗的に増大することが知られています。
参考)脂質異常症の合併症・検査・治療|品川・天王洲アイルの品川ワー…
脂質代謝異常における稀な症状と急性合併症
中性脂肪値が極端に高値(通常1000mg/dL以上)になると、急性膵炎を発症するリスクが著しく高まります。急性膵炎は激しい腹痛を主訴とし、時に致命的となる重篤な疾患であるため、高トリグリセリド血症の患者には特に注意が必要です。
中性脂肪値が非常に高くなると、肝臓や脾臓の腫大、手足のピリピリ感や灼熱感、呼吸困難、錯乱といった多彩な神経学的症状が出現することがあります。また、角膜の周辺部に乳白色または灰色の輪状の混濁(角膜輪)が認められることもあり、これは長期間にわたる脂質異常症の存在を示唆する所見となります。
発疹性黄色腫は、中性脂肪が極めて高値の際に出現する特殊な黄色腫で、全身の皮膚、特に臀部や背部、伸側面に多発性の小さな黄色の丘疹として急速に出現します。これらの症状は脂質異常症の重症度を反映しており、緊急の治療介入が必要な状態を示しています。
参考)黄色腫|代謝異常症②
脂質代謝異常における二次性要因の鑑別
脂質代謝異常症の中には、他の疾患に続発して発症する二次性(続発性)脂質異常症が存在し、原疾患の治療により脂質異常が改善する可能性があるため、その鑑別は臨床上重要です。甲状腺機能低下症は続発性脂質異常症の主要な原因疾患の一つであり、甲状腺ホルモンの低下により総コレステロール、LDLコレステロール、アポリポ蛋白Bの増加を認めます。
参考)トリグリセライド コントロールの重要性(スタッフ向け解説ペー…
甲状腺ホルモンの補充療法により脂質異常症の改善と動脈硬化の進展抑制が期待できるため、脂質異常症患者では甲状腺機能の評価が推奨されます。ネフローゼ症候群やクッシング症候群も続発性脂質異常症を引き起こす重要な疾患です。
参考)https://www.j-athero.org/jp/wp-content/uploads/publications/pdf/GL2022_s/06.pdf
糖尿病に伴う脂質異常症も広義の二次性脂質異常症と考えられますが、肥満やメタボリックシンドロームを基盤とする場合、インスリン抵抗性という共通の病態により糖代謝と脂質代謝の異常が同時に生じているため、単純な続発性とは言い切れない複雑な関係にあります。このような症例では、血糖値や脂質値の管理だけでなく、根本原因であるインスリン抵抗性の改善に焦点を当てた包括的な治療アプローチが必要となります。
参考)脂質異常症 href="https://motegi-clinic.jp/naika04/" target="_blank">https://motegi-clinic.jp/naika04/amp;#8211; もてぎ医院
医薬品の副作用として脂質異常症が出現することもあり、ステロイド薬、利尿薬、免疫抑制薬などの使用時には定期的な脂質プロファイルのモニタリングが重要です。
慶應義塾大学病院の脂質代謝異常症に関する包括的な診療情報と診断基準の詳細
日本動脈硬化学会による続発性脂質異常症の診断と管理に関するガイドライン
脂質代謝異常の診断と治療
脂質代謝異常の診断基準と検査方法
脂質代謝異常症の診断は、早朝空腹時(10時間以上の絶食)の血液検査により行われ、LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド(中性脂肪)、総コレステロールの測定が基本となります。日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、以下の診断基準が設定されています。
参考)脂質代謝異常症
脂質異常症の診断基準
| 病態 | 診断基準値 |
|---|---|
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール140mg/dL以上 |
| 境界域高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール120~139mg/dL |
| 高トリグリセライド血症(空腹時) | トリグリセライド150mg/dL以上 |
| 高トリグリセライド血症(随時) | トリグリセライド175mg/dL以上 |
| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール40mg/dL未満 |
| 高non-HDLコレステロール血症 | non-HDLコレステロール170mg/dL以上 |
これらの項目のうち1つでも基準を満たしていれば、脂質代謝異常症と診断されます。トリグリセライドが400mg/dL以上や随時採血の場合は、non-HDLコレステロール(総コレステロール-HDLコレステロール)またはLDLコレステロール直接法を使用します。
参考)脂質異常症の診断と治療
LDLコレステロールは通常、Friedewald式(総コレステロール-HDLコレステロール-トリグリセライド/5)で計算されますが、トリグリセライドが高値の場合は直接測定法が推奨されます。検査結果は通常1時間程度で確認可能であり、当日または翌日には結果が得られます。
参考)脂質異常症
脂質代謝異常の原因と危険因子
脂質代謝異常の原因は多岐にわたりますが、主に生活習慣に起因することが多く、遺伝的要因や他の疾患の影響も重要です。LDLコレステロール高値の主な原因は飽和脂肪酸の過剰摂取であり、肉の脂身、バター、生クリーム、インスタントラーメンなどの加工食品に多く含まれています。コレステロールを多く含む鶏卵、魚卵、レバーなどの摂取過多も要注意です。
参考)脂質異常症(高脂血症)の原因と治療法を解説|アイン薬局
脂質代謝異常の主要な危険因子
📌 遺伝的要因: 家族性高コレステロール血症などの遺伝性疾患があり、親や兄弟姉妹に高コレステロール血症や心疾患が多い場合はリスクが高まります
📌 食生活: 高脂肪・高カロリー・高糖質の食事が続くと発症しやすく、食物繊維不足もコレステロール値上昇の一因となります
📌 肥満: 特に内臓脂肪型肥満の人は、高コレステロール血症や高トリグリセリド血症のリスクが高くなります
📌 運動不足: 身体活動の不足は脂質異常症のリスクを高め、特にHDLコレステロールの低下と関連しています
参考)https://naika.m-seikei.net/blog/2024/05/30/%E8%84%82%E8%B3%AA%E7%95%B0%E5%B8%B8%E7%97%87%E3%81%AE%E5%85%A8%E3%81%A6%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC%EF%BC%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%81%8B%E3%82%89%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%BE%B9%E5%BA%95/
📌 喫煙: 血管を収縮させ血管内膜にダメージを与えるため、脂質異常症を引き起こすリスクが高まります
📌 加齢: 年齢とともに脂質代謝の能力が低下し、脂質異常症が発症しやすくなります
脂質代謝異常による合併症とリスク管理
脂質代謝異常を放置すると、動脈硬化を基盤とした多様な合併症を引き起こし、生命予後に重大な影響を及ぼします。最も重要な合併症は心血管疾患であり、特に冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患のリスクが顕著に増加します。
参考)https://www.mdpi.com/1422-0067/23/2/786/pdf
脂質代謝異常の主要合併症
| 合併症 | 病態と臨床的意義 |
|---|---|
| 冠動脈疾患 💔 | 冠動脈が狭窄・閉塞し心筋への酸素供給が低下、急性心筋梗塞や狭心症を引き起こす |
| 脳血管疾患 🧠 | 脳の血管が詰まるまたは破れることで脳卒中や一過性脳虚血発作を発症 |
| 閉塞性動脈硬化症 🦵 | 下肢の血管が詰まり歩行時の痛みや壊疽のリスクが増大 |
| 脂肪肝 🫘 | 肝臓に脂肪が蓄積し肝機能低下や炎症を引き起こし、肝線維症・肝硬変に進行する可能性 |
| 急性膵炎 ⚠️ | 極端な高トリグリセリド血症により膵臓に炎症が生じ、激しい腹痛や消化器症状を呈する |
| 慢性腎臓病 🫘 | 腎臓の血管障害により腎機能が低下し、老廃物の除去や水分調整が困難になる |
脂質異常症と高血圧が合併すると、動脈硬化を引き起こすメカニズムが相乗的に働き、合併症の発症・進行リスクが著しく高まります。脂質異常症により血液中のコレステロールが過剰になり血管内に沈着しやすくなった状態で、高血圧による血管への物理的ストレスが加わることで、動脈硬化の進行が加速されます。
参考)https://clinicplus.health/hypertension/dyslipidemiaandhypertension/
糖尿病、慢性腎臓病、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患などの既往がある場合は、脂質異常症との相互作用により合併症リスクが高まるため、早期の薬物療法の検討が必要です。
参考)脂質異常症の治療薬とは?種類・効果・副作用を解説 - 医療法…
脂質代謝異常の治療戦略:食事療法と運動療法
脂質代謝異常症の治療は、通常は食事療法と運動療法から開始します。薬物療法は、生活習慣の改善を行っても脂質管理の目標値が達成できない場合、または持っている危険因子が多く動脈硬化性疾患を起こすリスクが高い場合に開始されます。
参考)https://www.sageru.jp/ldl/treatment/
食事療法では、脂肪分の多い食品を避け、特に飽和脂肪酸の摂取を制限することが重要です。野菜や果物を多く摂取し、食物繊維を十分に確保することでコレステロール値の改善が期待できます。運動療法としては、定期的なウォーキングや水泳などの有酸素運動を週3回以上、1回30分程度行うことが推奨されます。
禁煙も脂質異常症の管理において非常に重要であり、喫煙は脂質異常症のリスクを高めるだけでなく、動脈硬化を直接的に促進するため、必ず禁煙指導を行う必要があります。適度な飲酒は問題ありませんが、アルコールの過剰摂取は特にトリグリセライド値を上昇させるため注意が必要です。
脂質代謝異常の薬物療法と管理目標
薬物療法は、LDLコレステロールや中性脂肪の数値を低下させることを目的とし、食事療法や運動療法で期待される効果が得られなかった場合に開始します。脂質異常症の治療薬には、主にスタチン系薬剤、フィブラート系薬剤、エゼチミブ、PCSK9阻害薬などがあり、患者の脂質プロファイルや合併症のリスクに応じて選択されます。
スタチン系薬剤はLDLコレステロールを効果的に低下させる第一選択薬であり、心血管イベントの予防効果が多数の大規模臨床試験で証明されています。フィブラート系薬剤は主にトリグリセライドを低下させ、HDLコレステロールを増加させる作用があります。
脂質異常症の治療目標値は、患者の動脈硬化性疾患の発症リスクに応じて層別化されており、糖尿病、慢性腎臓病、脳梗塞、心筋梗塞などの既往がある高リスク患者では、より厳格な管理目標値が設定されます。治療開始後も定期的な血液検査によるモニタリングが必要であり、目標値の達成状況と副作用の有無を継続的に評価する必要があります。
家族性高コレステロール血症などの遺伝性疾患では、生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られないため、早期からの積極的な薬物療法とカスケードスクリーニング(家族検診)が推奨されます。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10164595/
脂質異常症の包括的な治療戦略と管理目標値に関する詳細情報
脂質異常症の症状、原因、種類、疫学をわかりやすく解説した医療従事者向けガイド