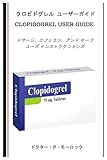クロピドグレルの副作用
クロピドグレルは血小板の凝集を抑制することで血栓形成を予防する抗血小板薬として、心筋梗塞や脳梗塞の再発予防に広く使用されています。その一方で、薬理作用に関連した出血傾向をはじめとする多様な副作用が報告されており、投与に際しては慎重なモニタリングが求められます。本剤はチクロピジンの重篤な副作用を軽減する目的で開発されましたが、依然として注意すべき有害事象が存在します。
参考)医療用医薬品 : クロピドグレル (クロピドグレル錠25mg…
クロピドグレルの主な副作用の種類と発現頻度
クロピドグレルの主な副作用として、肝機能検査値の異常が高頻度で認められます。臨床試験において、γ-GTP上昇が8.2%(47/575例)、ALT上昇が7.5%(43/575例)、AST上昇が5.9%(34/575例)と報告されており、これらは定期的な血液検査によるモニタリングが必要な項目です。また、皮下出血が4.9%(28/575例)、Al-P上昇が4.2%(24/575例)、鼻出血が3.0%(17/575例)の頻度で発現しています。
参考)クロピドグレル錠25mg「FFP」の効能・副作用|ケアネット…
比較試験では、チクロピジン塩酸塩の副作用発現率55.3%(219/396例)に対し、クロピドグレル硫酸塩は44.9%(178/396例)と有意に低値を示しました。この群間差は10.35%(両側95%信頼区間:3.43、17.28)であり、クロピドグレルの安全性プロファイルの優位性が示されています。
参考)クロピドグレル錠75mg「科研」の効能・副作用|ケアネット医…
クロピドグレルに特徴的な副作用として皮膚障害があり、皮疹、湿疹、掻痒感、類天疱瘡などが報告されています。発生機序は過敏症状の一つと考えられていますが、詳細なメカニズムは未だ明らかになっていません。一方、出血に関連する副作用はアスピリンと比較すると発現頻度が低いという特徴があります。
参考)全日本民医連
肝機能障害については、チクロピジンで問題となっていた重篤な肝障害のリスクはクロピドグレルで低減されていますが、他の抗血小板薬と比較すると依然として報告件数が多く、継続的なモニタリングが重要です。
クロピドグレルの重大な副作用:出血リスク
クロピドグレルの最も重要な副作用は、その薬理作用に起因する出血傾向です。重大な出血として、脳出血等の頭蓋内出血(1%未満)、硬膜下血腫(0.1%未満)、吐血(頻度不明)、下血、胃腸出血、眼底出血(いずれも1%未満)、関節血腫(0.1%未満)などが報告されています。
参考)クロピドグレル:どんな薬?費用や副作用は?日常生活の注意点は…
臨床症状として、突然の頭痛、吐き気・嘔吐、体の麻痺などが出現した場合は頭蓋内出血の可能性があり、直ちに医療機関への連絡が必要です。また、吐血、黒色便、視力低下、関節痛などの症状は、胃腸出血、眼底出血、関節血腫の可能性を示唆します。
冠動脈バイパス術施行例における重大な出血の発現率は59.26%(16/27例)と高率であり、特に術前の休薬期間が7日未満の症例では65.0%(13/20例)と、7日以上の症例の42.9%(3/7例)と比較して高い傾向が認められました。このことから、待機的手術においては適切な休薬期間の確保が出血リスクの低減に重要であることが示されています。
参考)クロピドグレル錠25mg「サワイ」の効能・副作用|ケアネット…
| 出血部位 | 発現頻度 | 臨床的特徴 |
|---|---|---|
| 頭蓋内出血 | 1%未満 | 突然の頭痛、意識障害、麻痺などを呈し、緊急対応が必要 |
| 消化管出血 | 1%未満 | 吐血、下血、黒色便として発現 |
| 眼底出血 | 1%未満 | 視力低下や視野障害を伴う |
| 皮下出血 | 4.9% | 比較的軽度だが、高頻度で認められる |
胃・十二指腸潰瘍も頻度不明ながら重要な副作用であり、出血を伴う胃潰瘍・十二指腸潰瘍があらわれることがあります。胃痛、嘔吐、吐血、下血などの症状に注意が必要です。
クロピドグレルによる肝機能障害と黄疸
クロピドグレルの投与により肝機能障害と黄疸が発現することがあり、重大な副作用として位置づけられています。具体的には、ALT上昇、γ-GTP上昇、AST上昇、Al-P上昇などの肝酵素の異常値が認められます。
比較試験のデータでは、クロピドグレル硫酸塩の主な副作用として、ALT増加が15.2%(60/396例)、AST増加が11.6%(46/396例)、γ-GTP増加が9.3%(37/396例)、血中ALP増加が6.1%(24/396例)と報告されており、肝機能に関連する異常が高頻度で発現することが示されています。
チクロピジンで深刻な問題となっていた肝障害について、クロピドグレルはそのリスクを低減する目的で開発されましたが、他の抗血小板薬と比較すると依然として肝機能障害の報告件数が多いという特徴があります。そのため、投与開始後2ヵ月間は2週間に1回程度の血液検査等の実施を考慮する必要があります。
参考)医療用医薬品 : クロピドグレル (クロピドグレル錠25mg…
臨床的には、黄疸、吐き気・嘔吐、食欲不振などの症状として現れることがあり、これらの症状に気づいた場合は速やかに医師または薬剤師に相談することが推奨されます。重篤な肝障害に進展する前に早期発見・早期対応を行うことが、患者の安全性確保において重要です。
参考)くすりのしおり : 患者向け情報
クロピドグレルと血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)はクロピドグレルの稀ながら重大な副作用の一つです。TTPは全身に小さな血栓が形成され、脳、心臓、腎臓などの重要臓器への血液の流れを妨げる病態であり、適切な対応が遅れると致命的となる可能性があります。
参考)クロピドグレルに関連した血栓性血小板減少性紫斑病 | 日本語…
クロピドグレル関連TTPの特徴として、投与開始後早期に発症する傾向があり、11例の報告された患者のうち10例までが投与開始後14日間以下で発症しています。チクロピジン関連TTPの発症率が投与患者1,600~5,000人当り1人と推定されているのに対し、クロピドグレルについては第III相臨床試験で20,000例の患者において1例も観察されなかったため、当初は極めて稀な副作用と考えられていました。
治療に関しては、報告された11例の患者のうち10例が血漿交換の処置に反応を示しましたが、そのうち2例は臨床上の改善が得られるまでに20回以上の血漿交換が必要でした。また、1例の患者は診断後ただちに血漿交換が行われたにもかかわらず死亡しており、TTPの重篤性が示されています。
医療従事者は、クロピドグレル投与開始後2ヵ月間、特に最初の2週間において、血小板減少、溶血性貧血、発熱、神経症状、腎機能障害などのTTPの徴候に注意を払う必要があります。これらの症状が認められた場合は、速やかに血液検査等を実施し、TTPが疑われる場合は投与を中止して適切な治療を開始することが重要です。
CYP2C19遺伝子型によるクロピドグレルの効果と副作用への影響
クロピドグレルはプロドラッグであり、主にCYP2C19により活性代謝物に変換されることで薬効を発揮します。そのため、CYP2C19の遺伝子多型が薬物動態および薬力学に大きな影響を与えることが知られています。
参考)CYP2C19 の遺伝子型がクロピドグレル治療の転帰に及ぼす…
CYP2C19の遺伝子型は大きく3つに分類されます:
参考)CYP2C19とクロピドグレル | 一般社団法人 日本血栓止…
📊 遺伝子型分類
- Extensive metabolizer(EM、CYP*1/*1): 変異を持たない正常代謝型
- Intermediate metabolizer(IM、CYP*1/*2、*1/*3): 1つの変異を持つ中間代謝型
- Poor metabolizer(PM、CYP*2/*2、*2/*3、*3/*3): 2つの変異を持つ機能欠損型
この遺伝子多型には人種差があり、日本人では18~23%が機能欠損型(PM)またはヘテロ接合体(IM)であるのに対し、欧米人では3~5%と低率です。これは日本人において遺伝子多型の影響を受けやすい患者の割合が高いことを意味します。
薬物動態においては、機能低下型(IMおよびPM)の患者では活性代謝物の血中濃度が非保有者(EM)と比較して有意に低値を示し、血小板凝集抑制作用も有意に低下します。臨床試験のデータでは、300mg負荷投与時のCmaxはEMで29.8±9.88 ng/mL、IMで19.6±4.73 ng/mL、PMで11.4±4.25 ng/mLと、遺伝子型によって明確な差が認められています。
この薬物動態の差は臨床効果にも影響し、機能喪失型対立遺伝子の保有者では心血管イベントの抑制効果が減弱する可能性が複数の大規模研究で示されています。一方、機能獲得型である*17を有する患者では、クロピドグレルによる血小板抑制作用が増強し、出血のリスクが増加すると報告されています。
このような遺伝子型による個人差を踏まえ、医療従事者は患者の治療効果や副作用のモニタリングをより慎重に行い、必要に応じて遺伝子検査の実施や投与量の調整、他の抗血小板薬への変更を考慮することが推奨されます。
クロピドグレル投与時の術前管理と休薬期間
クロピドグレルは抗血小板作用により周術期の出血リスクを増加させるため、待機的手術においては適切な休薬期間の設定が重要です。一般的に、クロピドグレルの術前休薬期間は5~7日間とされています。
参考)https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/medicine/wp-content/uploads/Dinews201811-1.pdf
手術リスク別の休薬期間の目安
- 中-高リスク手技: 7日前に中止
参考)https://www.shimizuhospital.com/dist/wp-content/uploads/2023/12/c74cd05a7e18ebe0ddd4f86bf2f43079.pdf
- 出血リスクが高い場合: 5~7日前に中止
参考)https://www.hsp.ehime-u.ac.jp/medicine/wp-content/uploads/202108-1DInews2.pdf
- 低リスク手技: 休薬不要な場合もある
冠動脈ステント留置患者や血栓塞栓症の2次予防などの理由で服用している場合には、5日程度の短い休薬期間も考慮されることがあります。しかし、冠動脈バイパス術施行例では、術前の休薬期間が7日未満の症例で重大な出血の発現率が65.0%と、7日以上の症例の42.9%と比較して高いことが報告されており、可能な限り十分な休薬期間を確保することが望ましいとされています。
術後の抗血小板薬の再開に関しては、負荷投与後24~72時間以内に再開することが推奨されています。ただし、高リスク手技では術後の出血により48~72時間以降を考慮することもあります。多剤併用の場合は症例に応じて慎重に対応する必要があり、特に冠動脈ステント留置後の患者では、ステント血栓症のリスクと出血リスクのバランスを慎重に評価することが求められます。
参考)術前の抗血栓薬、止める期間は今でも1週間?
愛媛大学医学部附属病院の抗血小板薬・抗凝固薬の手術前休薬期間のガイドライン(術前休薬の具体的な期間と注意事項が詳細に記載されています)
休薬期間はあくまでも目安であり、実際の休薬および手術可否の判断は、患者の基礎疾患、手術の種類、出血リスクと血栓リスクのバランスを総合的に評価して決定する必要があります。特に、以下の高リスク病態では休薬のタイミングや代替療法について慎重な検討が必要です:
参考)https://www.kameda.com/pr/pharmacy/pdf/before_surgery.pdf
🔴 高リスク病態の例
- 冠動脈ステント留置後2ヶ月以内
- 冠動脈薬剤溶出性ステント留置後12ヶ月以内
- 脳血行再建術後の患者
クロピドグレルの薬物相互作用と併用注意薬
クロピドグレルは他の薬剤との相互作用により、その効果や副作用のリスクが変化する可能性があります。特に重要な相互作用として、CYP2C19の活性に影響を与える薬剤との併用が挙げられます。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000671529.pdf
強力なCYP2C19誘導薬との相互作用
リファンピシン等の強力なCYP2C19誘導薬との併用は避けることが望ましいとされています。クロピドグレルは主にCYP2C19によって活性代謝物に代謝されるため、CYP2C19酵素を誘導する薬剤との併用により、本剤の活性代謝物の血漿中濃度が増加し、血小板阻害作用が増強されることにより出血リスクが高まるおそれがあります。
参考)https://medical.nihon-generic.co.jp/a.php?id=40
セレキシパグとの併用注意
セレキシパグとクロピドグレルの併用では、セレキシパグの活性代謝物(MRE-269)のCmax及びAUCが増加したとの報告があります。これは、クロピドグレルのグルクロン酸抱合体によるCYP2C8阻害作用により、セレキシパグの血中濃度が増加すると考えられています。本剤と併用する場合には、セレキシパグの減量を考慮することが推奨されます。
モルヒネとの相互作用
モルヒネとの併用により、本剤の血漿中濃度が低下するおそれがあります。これは、モルヒネの消化管運動抑制により、本剤の吸収が遅延すると考えられています。
出血リスクを増加させる薬剤
クロピドグレルと他の抗血栓薬(抗凝固薬、抗血小板薬)との併用は、出血リスクを著しく増加させる可能性があります。アスピリンと併用した時、クロピドグレル単剤に比べ重大な出血の発現率の増加が海外で報告されています。
参考)https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00065380.pdf
医療従事者は、クロピドグレルを処方する際には患者の併用薬を十分に確認し、相互作用のリスクを評価する必要があります。特に、新たに薬剤を追加する際や、他の医療機関で処方された薬剤がある場合には、薬剤師と連携して相互作用の有無をチェックすることが重要です。
厚生労働省によるセレキシパグ及びクロピドグレル硫酸塩含有製剤の併用に関する資料(薬物相互作用の詳細なメカニズムと対応策が記載されています)