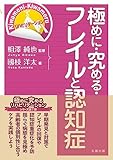フレイルの症状と診断基準
フレイルとは、英語の「Frailty(虚弱)」の日本語訳で、加齢に伴い心身の活力が低下し、生活機能が障害された状態を指します。日本老年医学会は2014年に、適切な介入により健常な状態に戻る可逆性が含まれることを強調して「フレイル」という用語の使用を提唱しました。フレイルは健康な状態と要介護状態の中間に位置し、多くの高齢者はフレイルを経て要介護状態へ進むと考えられています。
参考)フレイルの診断
フレイルの症状は多面的で、身体的問題だけでなく認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題、独居や経済的困窮などの社会的問題も含む包括的な概念です。早期発見と適切な介入により機能の回復・向上を図れる可逆性があるため、医療従事者による早期発見が重要です。
参考)「フレイル」を知っていますか?
フレイルの診断基準(J-CHS基準)の5項目
フレイルの診断には、Friedらが提唱したCHS基準が国際的に広く用いられており、日本では日本版CHS基準(J-CHS基準)が2020年に改訂されました。J-CHS基準は以下の5項目で構成されます。
参考)日本語版フレイル基準(J-CHS基準)を改定(国立長寿医療研…
- 体重減少:6か月で2kg以上の意図しない体重減少
- 筋力低下:握力が男性28kg未満、女性18kg未満
- 疲労感:ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがする
- 歩行速度:通常歩行速度が1.0m/秒未満
- 身体活動:軽い運動・体操、定期的な運動・スポーツのいずれも週に1回もしていない
判定基準として、5項目のうち3項目以上に該当する場合を「フレイル」、1~2項目に該当する場合を「プレフレイル」、該当なしを「ロバスト(健常)」と分類します。プレフレイルは、フレイルへ進行する前の段階であり、この時点での介入が特に重要です。
参考)要介護を食い止めるフレイル高齢者の薬物療法の秘訣
フレイル症状のセルフチェック方法
医療従事者が患者に推奨できるフレイルチェックの方法として、東京大学高齢社会総合研究機構が開発した「フレイルチェック」があります。これは市民が主体となって行える評価方法で、簡易チェックと総合チェックの2段階で構成されています。
参考)http://www.kda8020.or.jp/wp-content/uploads/2023/05/01.pdf
簡易チェックには「指輪っかテスト」と「イレブンチェック」が含まれます。指輪っかテストは、両手の親指と人差し指で輪を作り、ふくらはぎの最も太い部分を囲んで筋肉量を評価する方法です。イレブンチェックは、栄養・口腔・運動・社会性・うつなど11項目の質問により、身体的・精神的・社会的な3つの側面を評価できます。
厚生労働省が発表している「後期高齢者の質問票」も、医療・介護の両方の視点から高齢者の状態をスクリーニングするツールとして活用されています。基本チェックリスト25項目中7項目以上該当する場合をフレイルと判定する方法も用いられています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001068471.pdf
フレイル症状とサルコペニアの違い
サルコペニアとフレイルは密接に関連していますが、概念の範囲が異なります。サルコペニアは、加齢や疾患により筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態を指す身体的な問題です。一方、フレイルはサルコペニアを含むより広い概念で、身体的問題に加えて認知機能の低下、気分の落ち込み、社会的なつながりの減少など、心身のさまざまな機能低下を包含します。
参考)【図解】サルコペニアとは?フレイルとの違いは?特徴や対策方法…
サルコペニアは筋肉量と筋力の低下という主に身体機能の低下を示すのに対し、フレイルは身体的だけでなく精神・心理的、社会的な衰弱や虚弱も含みます。つまり、サルコペニアはフレイルの一部として位置づけられ、フレイルに至る重要なリスク因子の一つとなっています。医療従事者は、筋肉量や筋力の評価だけでなく、精神面や社会面も含めた包括的な評価が必要です。
参考)フレイルとサルコペニアの違いは何?共通する3つの予防法
フレイル症状が引き起こすリスクと合併症
フレイルを放置すると、さまざまな合併症や負のアウトカムが生じます。主要なリスクとして、転倒・骨折、術後合併症、要介護状態、認知症、施設入所、死亡などがあり、いずれもフレイルと有意な関連性が認められています。
参考)【図解】フレイルとは?主な原因と3つの対策【フレイルチェック…
フレイル高齢者は生活の質が低下するだけでなく、転倒や骨折のリスクが高まります。また、フレイルは認知機能障害を合併しやすく、横断調査ではフレイルの約20~55%に認知機能障害を合併しています。縦断調査では、フレイル高齢者は認知機能が低下しやすく、特に血管性認知症になりやすいことが示されています。
参考)日本サルコペニア・フレイル学会
さらに、フレイルと認知機能障害を合併すると、手段的ADL・基本的ADL・身体機能が低下しやすく、死亡率も高くなります。糖尿病などの生活習慣病の発症にも関連することがわかっており、慢性疾患の管理が不十分な場合、フレイルを悪化させる可能性があります。プロセスとしては、健常な状態からプレフレイルを経てフレイルへと進行し、さらに進行すると不可逆的な要介護状態に陥るため、早期段階での予防が極めて重要です。
参考)フレイルの予防
フレイル症状の多面性:身体・精神・社会的側面
フレイルは単一の症状ではなく、多面的な特性を持つ包括的な概念です。身体的フレイルとして、筋力低下、歩行速度低下、体重減少、疲労感、身体活動低下が代表的な症状ですが、これに加えて精神・心理的側面と社会的側面が相互に影響し合っています。
参考)総論 フレイルの全体像を学ぶ 1. フレイルとは:多面性とフ…
精神・心理的フレイルには、認知機能障害やうつなどが含まれます。気分の落ち込みが続く、物忘れが気になるといった症状は、身体的活動の低下を招き、さらにフレイルを進行させる悪循環を生み出します。社会的フレイルとしては、独居、経済的困窮、社会交流機会の減少などが挙げられます。
参考)フレイルの原因
これらの多面性を考慮すると、フレイルを有する高齢者においては、身体機能の評価だけでなく、認知・心理・精神的な側面や社会的な側面からのリスクを把握する必要があります。医療従事者は、栄養、歯科口腔、運動、社会性、うつなど複数の領域を包括的に評価し、個々の患者に合わせた多面的な介入を計画することが求められます。フレイルサイクルを断つためには、身体的・精神心理的・社会的フレイルそれぞれに対応した包括的な支援が不可欠です。
参考)フレイルサイクルを断つために実際に行った対応策とは?
フレイルの症状に対する予防と介入
フレイル症状の予防における3つの柱
フレイル予防には「栄養・運動・社会参加」の3つが基本の柱とされており、これに加えて近年は口腔ケアの重要性も認識されています。フレイルは可逆性という特性を持つため、早期から予防に取り組むことで健康な状態に戻ることが期待できます。
参考)フレイルの原因や予防方法とは?3つの柱や食事のちょい足しまで…
栄養面では、高齢者は摂取カロリー不足や栄養バランスの悪化が生じやすいため、適切な情報提供が重要です。低栄養はフレイル発症のリスク因子であり、ビタミンD、野菜、果物、魚の摂取量低下がリスクを高めます。特に高齢女性では、タンパク質の摂取がフレイル発症リスクを下げる可能性が示唆されていますが、運動との併用が推奨されます。
運動療法は、サルコペニアや筋力低下に対して、高齢者であっても筋力を維持・向上させる効果が報告されています。ただし、個人に合った運動から始めることが大切で、筋力が低下している状態で無理に運動すると転倒や骨折を起こす危険があります。社会参加は、人とのつながりや生活の広がりを維持し、歯や口腔機能を含む多岐にわたる健康分野に関与します。
フレイル症状の改善に効果的な栄養管理
フレイルの栄養管理では、運動療法とセットで行うことが必須です。低栄養状態で運動を行っても筋肉がつかないどころか、低栄養状態を助長してしまいます。筋肉をつけるために必要な良質なタンパク質を摂取できるような食事指導が重要です。
具体的な栄養改善策として、宅配食の利用や冷凍食品・缶詰などの活用が挙げられます。高齢者のタンパク質摂取量を増やす方法として、今までの食事に「ちょい足し」を指導することが効果的です。チーズやヨーグルト、卵、納豆、豆腐などは調理もほとんど不要で、誰でも追加しやすい食材です。
参考)https://www.tmghig.jp/research/topics/202402-15307/
オーラルフレイルと栄養の関係も重要です。オーラルフレイルを放置すると栄養不良、特に低栄養状態に陥る可能性があり、低栄養は余命や健康余命に対する独立したリスクとなります。健常な状態では、肉や野菜など噛み応えのあるものを積極的に取り入れ、具材を大きめにカットするなど、あえてよく噛むことで咀嚼機能を維持することが推奨されます。よく噛めるグループに比較して噛めないグループは多くの栄養素や食品群の摂取が低下するため、口腔機能の維持が栄養状態の確保に直結します。
参考)オーラルフレイルと栄養
フレイル症状に対する運動療法とリハビリテーション
高齢者に対する適切な運動療法は、サルコペニアや筋力低下の改善に効果があることが研究で報告されています。運動療法は個人に合ったものから始めることが大切で、段階的に運動強度を調整する必要があります。
運動の進め方として、最初はベッドの上で足の運動を行うことから始め、次に椅子に座ったり立ち上がったりを繰り返し、徐々に歩行距離を延ばしていくという段階的アプローチが推奨されます。筋力が低下している状態で、いきなり立ち上がったり無理に歩行しようとすると転倒や骨折を起こす危険があるため、慎重な評価と計画が必要です。
フレイルサイクルを断つためのリハビリテーションでは、身体的フレイル、精神心理的フレイル、社会的フレイルそれぞれに対応した包括的な介入が重要です。実際の症例では、退院後に隠居生活が予想される独居高齢者に対して、身体機能の回復だけでなく、社会交流の促進や趣味活動の導入など、多面的な支援を提供することでフレイルへの進行リスクを軽減できた事例が報告されています。
フレイル症状とオーラルフレイルの関連
オーラルフレイルは、滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、かめない食品が増えるなど、ささいな口腔機能の低下から始まります。これらの様々な口の衰えは、身体の衰え(フレイル)と大きく関わっています。オーラルフレイルは口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含み、身体の衰えの一つとして位置づけられます。
オーラルフレイルの特徴は、健康と機能障害との中間にあり可逆的であることです。早めに気づき適切な対応をすることでより健康に近づくことができます。オーラルフレイルの始まりは、滑舌低下、食べこぼし、わずかなむせ、かめない食品が増える、口の乾燥など、見逃しやすく気づきにくい症状であるため注意が必要です。
対応方法として、歯周病やむし歯などで歯を失った際には適切な処置を受けることはもちろん、定期的に歯や口の健康状態をかかりつけの歯科医師に診てもらうことが非常に重要です。毎日の正しいブラッシングと定期的な歯科受診が基本となります。また、地域で開催される介護予防事業などの口腔機能向上のための教室やセミナーを活用することも効果的です。
フレイル症状の早期発見における医療従事者の役割
フレイルは早期に発見し、適切な介入を行うことで機能の回復・向上を図れる可逆性があるため、医療従事者による早期発見が極めて重要です。医療従事者は、在宅や地域でフレイル予防に取り組む看護師や多職種との連携が求められます。
参考)フレイルの早期発見で、いくつになっても元気に!~在宅医療を支…
フレイルの早期発見のポイントとして、基本チェックリスト25項目を活用した定期的なスクリーニングが有効です。医療保険者が実施する高齢者の医療の確保に関する法律に基づく質問票を用いて、医療・介護の両方の視点から高齢者の状態をスクリーニングし、社会参加の促進を含むフレイル予防等の取り組みを実施することが推奨されています。
参考)働く世代からのフレイル予防/大阪府(おおさかふ)ホームページ…
持病のコントロールもフレイル予防の重要な要素です。糖尿病や高血圧、腎臓病、心臓病、呼吸器疾患、整形外科的疾患などの慢性疾患がある場合、まず持病のコントロールをすることが必要です。持病の治療がうまくいっていないとフレイルを悪化させてしまう可能性があり、また高齢者は体を動かすという気持ちになれないこともあります。フレイルと薬剤は密接な関係にあり、低血糖や低血圧を含むふらつきや転倒のリスク、認知機能への影響、食欲への影響などを考慮した薬物療法の調整が重要です。
医療従事者は、フレイルの多面性を理解し、身体的・精神的・社会的な側面から包括的に患者を評価し、個々の状況に応じた適切な介入を提供する役割を担っています。