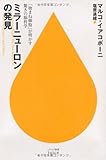神経線維と神経細胞の違い
神経細胞(ニューロン)の基本構造と役割
神経細胞は、神経系の構成単位として情報処理と伝達を担う特殊な細胞です。神経細胞は細胞体、樹状突起、軸索という3つの主要な構造から構成されており、それぞれが異なる機能を持っています。細胞体には核が存在し、細胞の栄養と代謝の中心として機能します。
参考)神経情報の伝達のしくみ(1)|神経系の機能
樹状突起は細胞体から枝分かれして伸びる複数の突起で、他の神経細胞からの電気信号を受け取る入力部として働きます。樹状突起は基部で太く、末端に向かうにつれて細くなる特徴的な形態を示します。一方、軸索は細胞体から伸びる通常1本の長い突起で、電気信号を他の神経細胞や効果器に伝える出力部として機能します。
参考)やさしくわかる病気事典:神経系しんけいけいの大おおまかな説明…
神経細胞は、細胞体で受け取った情報を統合し、一定の閾値を超えると活動電位を発生させてシナプスを通じて次の神経細胞に情報を伝達します。この情報伝達メカニズムにより、神経系は複雑な情報処理を可能にしています。人間の脳には数百億もの神経細胞が存在し、それらが複雑なネットワークを形成することで高次機能を実現しています。
神経線維の構造と有髄・無髄の分類
神経線維は、神経細胞の軸索とそれを包む支持細胞から構成される電気信号の伝導路です。医学分野では「神経線維」、生物学分野では「神経繊維」の表記が使われますが、同じ構造を指します。神経線維は、軸索を取り囲む支持細胞の被覆状態により、有髄神経線維と無髄神経線維に分類されます。
参考)「神経線維」の用語の意味
有髄神経線維では、中枢神経系ではオリゴデンドロサイト、末梢神経系ではシュワン細胞が軸索の周囲に何重にも巻きついて髄鞘(ミエリン鞘)を形成します。髄鞘は脂質に富んだミエリンという物質で構成され、絶縁体として機能します。髄鞘は一定間隔で途切れており、この途切れた部分をランビエ絞輪と呼びます。
参考)髄鞘 - Wikipedia
有髄神経線維では、活動電位がランビエ絞輪から絞輪へと跳躍するように伝わる「跳躍伝導」が起こります。この跳躍伝導により、有髄神経線維は無髄神経線維と比較して格段に速い伝導速度を実現しています。運動神経や知覚神経など、迅速な情報伝達が必要な神経は有髄神経線維で構成され、伝導速度は45〜120m/秒に達します。一方、自律神経の節後線維など、それほど速度を必要としない神経は無髄神経線維で構成され、伝導速度は0.4〜2.0m/秒程度です。
参考)有髄線維 - 脳科学辞典
髄鞘は単なる絶縁体としてだけでなく、軸索との間で物質交換を行い、神経軸索の栄養と保護など様々な神経機能を調節する重要な役割も担っています。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4691794/
神経線維における軸索の生理学的機能
軸索は神経細胞の細胞体から伸びる突起の中で、形態的に樹状突起と区別される特殊な構造です。軸索は基部で細く、そのまま末梢まで全長でほぼ同じ太さを保つという特徴的な形態を示します。神経細胞につき通常1本存在し、その神経細胞から伸びる最も長い突起であることが多く、末梢神経では1mに達するものもあります。
参考)軸索 - 脳科学辞典
軸索の主要な機能は、電気的興奮を伝えるという情報の出力を担うことです。軸索内ではタンパク質の合成がほとんど行われないため、軸索内およびシナプス領域で必要なタンパク質のほとんどは細胞体で合成された後、軸索輸送という機構によって運ばれます。軸索輸送では、キネシンやダイニンといったモータータンパク質が、微小管に沿って膜小器官やタンパク質複合体を両方向性に運んでいます。
参考)軸索輸送 - 脳科学辞典
軸索輸送には速い軸索輸送(50〜400mm/日)と遅い軸索輸送(8mm/日未満)があり、ミトコンドリアやシナプス小胞前駆体などの膜小器官は速い輸送で、チュブリンやニューロフィラメントなどの細胞骨格タンパク質は遅い輸送で運ばれます。この軸索輸送は、神経細胞の生存、形態形成、機能発現にとって基本的かつ重要な役割を果たしています。
軸索の末端部は神経終末と呼ばれ、ここにシナプス小胞が集積しています。活動電位が神経終末に到達すると、カルシウムイオンチャネルが開き、流入したカルシウムイオンがシナプス小胞を刺激して、神経伝達物質がシナプス間隙に放出されます。
参考)【高校生物】「伝達のメカニズム」
神経細胞と神経線維の中枢神経系における分布
中枢神経系である脳と脊髄の断面を観察すると、灰白質と白質という2つの異なる領域が確認できます。灰白質は神経細胞の細胞体が集まる領域で、色が濃く灰色がかった色を呈します。一方、白質は神経細胞体がなく神経線維が多く存在している領域で、髄鞘中のミエリンによって白く見えます。
参考)灰白質 - 脳科学辞典
大脳では、灰白質の大部分は表面の大脳皮質に位置し、その深部に白質である大脳髄質が広がります。ただし、大脳の深部の白質部にも島のように灰白質が存在し、これを大脳基底核と呼びます。脊髄では逆に、中心部に灰白質が位置し、その周囲を白質が取り囲む構造をしています。
参考)中枢神経系|神経系の機能
白質に含まれる神経線維は、異なる脳領域や脊髄と脳を連絡する情報伝達路として機能しており、これらの連絡路の配置と機能は神経系の正常な働きに不可欠です。白質には通常神経細胞体は存在しないとされていますが、実際には間質ニューロンと呼ばれる神経細胞が少数ながら存在することも報告されています。
参考)https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/neuro.05.007.2009/pdf
灰白質と白質の分布パターンと構造の理解は、脳卒中や脱髄疾患などの神経疾患の病態把握や画像診断において重要な意味を持ちます。MRIなどの画像検査では、灰白質と白質のコントラストの違いを利用して脳の構造と病変を評価します。
シナプス伝達における神経線維の役割
シナプスは、神経細胞間で情報を伝達する接合部であり、シナプス前膜、シナプス間隙、シナプス後膜から構成されます。神経線維の末端である軸索終末がシナプス前部を形成し、ここで電気信号が化学信号に変換されて次の神経細胞に情報が伝達されます。
参考)シナプス - 脳科学辞典
活動電位が軸索を伝導してシナプス前終末に到達すると、電位依存性カルシウムイオンチャネルが開き、細胞外から細胞内へカルシウムイオンが流入します。流入したカルシウムイオンがシナプス小胞を刺激し、シナプス小胞の膜と神経終末の細胞膜が融合することで、シナプス小胞に含まれる神経伝達物質がシナプス間隙に放出されます。
放出された神経伝達物質は、シナプス間隙を拡散してシナプス後膜上の受容体に結合し、シナプス後細胞の膜電位を変化させます。神経伝達物質受容体には、イオンチャネル型受容体と代謝調節型受容体があり、前者は直接膜電位を変化させ、後者は細胞内二次メッセンジャーを活性化します。
参考)シナプス伝達|生体機能の統御(2)
シナプス伝達には、神経伝導とは異なる特徴があります。神経線維における伝導は両側性、隔絶性、不減衰性という3つの原則に従いますが、シナプス伝達は一方向性であり、シナプス遅延が存在し、興奮の加重や後発射が起こります。また、シナプス伝達は薬物の影響を受けやすく、疲労しやすいという特性も持ちます。
参考)https://rehaac.org/pdf/shinkei_kiso.pdf
神経線維の機能異常は、シナプス伝達の障害を引き起こし、様々な神経疾患の原因となります。たとえば、脱髄疾患では髄鞘が破壊されることで神経伝導速度が低下し、正常なシナプス伝達が妨げられます。
看護roo! - シナプス伝達の詳細な解説
シナプス伝達のメカニズムと神経伝達物質の役割について、医療従事者向けに詳しく解説されています。
脳科学辞典 - 軸索輸送
軸索輸送の分子メカニズムと神経細胞の機能維持における重要性について、最新の知見が網羅的にまとめられています。
脳科学辞典 - 有髄線維
有髄神経線維の構造、髄鞘形成のメカニズム、跳躍伝導の原理について、分子レベルから詳細に解説されています。