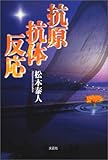抗原抗体反応と生物基礎
抗原抗体反応の基本的な仕組みと特異性
抗原抗体反応は、体内に侵入した異物である抗原に対して、免疫システムが産生した抗体が特異的に結合する反応です。この反応は「鍵と鍵穴」の関係に例えられ、ある抗原に対する抗体は、その抗原としか結合できないという高い特異性を持っています。抗原にはウイルス、細菌、真菌、寄生虫、花粉などの自然界に存在するものから、人工的な化学物質まで多様な種類があります。一方、抗体はγグロブリンと呼ばれるタンパク質の一種で、侵入してきた異物と結合する性質を持っています。
参考)https://manapedia.jp/text/851
抗原と抗体の結合部位は非常に限定された領域で起こります。抗原側の決定群(エピトープ)と抗体側の抗原結合部位(パラトープ)が接触し、水素結合、静電力結合、ファン・デル・ワールス力、疎水性反発力などの非共有結合によって結びつきます。これらは可逆的な結合であるため、一度結合した抗原抗体複合体も分子運動により解離することがあります。結合と解離が平衡状態に達するまでの時間は極めて短く、平衡状態はきわめて短時間内に達成されます。
参考)抗原と抗体の相互作用とは【抗体技術の基本原理】 - M-hu…
抗体の親和性は、抗原と抗体の結合強度を示す指標です。親和性は平衡解離定数(K_D)の逆数で表され、K_D値が低いほど親和性が高く、目的タンパク質と強固に結合します。親和性の高い抗体は臨床検査や免疫沈降などの実験技術において重要な役割を果たし、存在量の少ないタンパク質でも効率的に捕捉することが可能です。特異性と親和性は密接に関連しており、多くの場合、高い特異性は高い親和性を伴います。
参考)https://www.ptglab.co.jp/news/blog/antibody-specificity-and-affinity-in-immunoprecipitation/
抗原抗体反応における免疫グロブリンの構造と種類
抗体は免疫グロブリン(Ig)と呼ばれ、Y字型の構造を持つタンパク質です。2本の同一の重鎖と2本の同一の軽鎖がジスルフィド結合によって結合した構造をしています。Y字の先端部分には可変部(V領域)があり、この部分が抗原と直接結合します。可変部の配列は抗体ごとに異なり、特定の抗原を認識する特異性を決定します。一方、Y字の根元部分は定常部(C領域)と呼ばれ、抗体のクラスを決定し、補体の活性化やマクロファージとの相互作用などのエフェクター機能を担います。
参考)【高校生物基礎】「抗体の構造」
免疫グロブリンは5つの主要なクラスに分類されます。IgGは血液中に最も多く存在し、胎盤を通過して胎児に受動免疫を提供する能力があります。IgGはさらにIgG1、IgG2、IgG3、IgG4の4つのサブクラスに分類され、それぞれ機能特性が異なります。IgMは抗原に反応して最初に産生される抗体で、五量体構造により効果的な凝集と補体活性化を可能にします。IgAは主に消化管や呼吸器などの粘膜領域に存在し、粘膜免疫において重要な役割を果たします。血清IgA(単量体)と分泌型IgA(二量体)の2つの形態があります。
参考)免疫グロブリン抗体の理解:構造、機能、種類 - Assay …
各免疫グロブリンクラスは重鎖のタイプによって区別され、IgG分子はγ鎖、IgM分子はμ鎖を持ちます。IgG抗体の抗原結合部位はIgMよりも抗原への親和性が高い傾向にありますが、IgMは五量体構造により10個の抗原結合部位を持つため、結合活性(アビディティ)が高くなります。このような構造的特徴により、各免疫グロブリンクラスは免疫応答の異なる段階で特異的な役割を果たしています。
参考)研究用抗体とは?
抗原提示とヘルパーT細胞による免疫応答の調節
体内に抗原が侵入すると、樹状細胞やマクロファージなどの抗原提示細胞が抗原を食作用によって取り込み分解します。分解された抗原の一部(ペプチド抗原)は、主要組織適合遺伝子複合体クラスII分子(MHC クラスII)の上に乗せられ、細胞表面に提示されます。この過程を抗原提示と呼びます。B細胞も自身が持つB細胞レセプター(抗体分子)で病原体を捕捉して取り込み、分解後にクラスII分子上にペプチド抗原を提示します。
参考)https://www.obunsha.co.jp/pdf/support/9784010340004-p130_147.pdf
ヘルパーT細胞は樹状細胞に提示された抗原を認識すると活性化されます。活性化したヘルパーT細胞は、同一の抗原を提示しているB細胞と出会うと、B細胞上の「クラスII+ペプチド」によって再活性化され、B細胞の増殖を促進します。このヘルパーT細胞とB細胞の相互作用により、病原体と特異的に結合できる抗体が産生されます。B細胞は形質細胞(抗体産生細胞)に分化し、その抗原に特異的に結合する抗体を作り、血液中に放出します。
参考)ウイルスに対する免疫応答の仕組み(2)│コロナ制圧タスクフォ…
抗体は抗原と結合し、溶菌・凝集させて無毒化し、病原体を排除します。抗体は侵入してきた抗原と結合して周囲を取り囲み、毒となる部分を隠して動けなくします。また、細菌が作り出す毒素も無毒化します。この一連の免疫応答プロセスは、抗原提示細胞、ヘルパーT細胞、B細胞の協調的な働きによって成立しており、獲得免疫の中心的なメカニズムです。
参考)免疫において重要な「抗体」とは?仕組みや役割を徹底解説!
抗原抗体反応の一次免疫応答と二次免疫応答の違い
最初にウイルスなどの病原体に感染した時に起こる免疫反応を一次応答と呼びます。一次応答では、まず偵察の役割を持つIgM抗体が働き始めます。しかし、初回の感染では形質細胞の数が少なく、抗体も多くは作られません。抗原が体内に初めて侵入した際、その抗原を認識できるB細胞やT細胞は限られているため、免疫応答の立ち上がりには時間がかかります。一次応答で産生される抗体量は比較的少なく、抗体の親和性も低い傾向にあります。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1885586/
一次応答で反応したB細胞やキラーT細胞の多くは、病原体が体内から消滅すると死滅します。しかし、一部のB細胞やキラーT細胞は感染の記憶を残したままメモリーB細胞やメモリーT細胞となって体内に長期間生存し続けます。メモリー細胞は一次応答の際の記憶を引き継いでいるため、次に同じ病原体が侵入してきた時には、一次応答の時よりも早く反応し、病原体を攻撃したり抗体を作り出したりすることができます。
参考)免疫応答とは?免疫細胞の役割や反応の流れを詳しく解説!
2回目以降の同じ病原体の侵入に対する免疫反応を二次応答と呼びます。二次応答では、記憶細胞がすぐに病原体の情報を認識し、その病原体に適したIgG抗体を迅速に産生します。二次応答で作られる抗体は一次応答の時に比べて数が多く、生存期間も長いという特徴があります。また、二次応答ではIgGの産生が早いため、免疫反応を速やかに起こすことができ、感染症の軽症化が期待できます。ジフテリアやおたふく風邪など、一度感染すると二度目以降はかからない感染症があるのは、この免疫記憶のメカニズムによるものです。
参考)免疫応答って何?免疫のしくみや免疫に異常が起こった場合を解説…
抗原抗体反応の種類と臨床応用における独自視点
抗原抗体反応には様々な種類があり、それぞれ臨床検査や研究に応用されています。沈降反応は、水に溶ける抗原と抗体を適切な割合で混合すると、抗原抗体複合体が凝集して不溶性の沈降物を形成する反応です。抗原が多すぎても抗体が多すぎても沈降物はできず、適切な比率(当量点)で最大の沈降が観察されます。寒天ゲルを用いたOuchterlony法や一元平板免疫拡散法などが沈降反応を利用した検査法として知られています。
参考)抗原抗体反応(コウゲンコウタイハンノウ)とは? 意味や使い方…
凝集反応は、抗原が赤血球のような巨大粒子の表面にある場合に、抗体との反応によって粒子が凝集する現象です。凝集反応は沈降反応に比べて反応時間が短く(数分から1時間)、わずかな抗体量(1億分の1グラム程度)でも反応するため、抗体の検出に広く用いられています。ラテックス凝集反応などは、非常に鋭敏に抗原を検出する方法として臨床検査で使用されています。血液型検査も凝集反応の代表的な応用例であり、血液中の抗原と抗体が出会うと赤血球が凝集して塊を作ります。
参考)https://www.cosmobio.co.jp/support/technology/milk-protein/milk-protein-05.asp
免疫比濁法や比ろう法は、抗原に抗体を反応させて免疫複合体の沈降物を形成させ、その凝集塊に光を照射して散乱による照射光の減衰を測定する方法です。この技術は自動分析器で計測でき、血清中のタンパク質濃度の定量に広く利用されています。ELISA法(酵素免疫測定法)は抗体と反応する物質を検出する非常に鋭敏な方法の一つで、96穴のマイクロプレートを反応容器として使用します。酵素標識した二次抗体を用いることで、微量の抗原でも高感度に検出・定量できます。
参考)比濁法と比ろう法
近年の研究では、抗体の多反応性(ポリリアクティビティ)が注目されています。従来、抗体は単一の抗原にのみ結合すると考えられてきましたが、実際には一部の抗体は特定の抗原に高い親和性で結合すると同時に、関連するタンパク質や無関係な標的にも低い親和性で結合することがあります。この多反応性は自然免疫における柔軟な防御機構として機能する一方で、治療用抗体では標的外タンパク質への結合による機能喪失のリスクとなります。抗体の構造柔軟性が多反応性に関与しており、CDRループ領域の生化学的パターンが多反応性の予測因子となることが明らかになっています。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7755423/
免疫沈降法は、抗体の特異性を利用して混合物中から目的タンパク質を分離・精製する技術です。抗体を担体に固定化したアフィニティークロマトグラフィーは汎用されており、中性pHで低イオン強度の緩衝液を用いると抗原抗体複合体が形成され、0.1M酢酸溶液などで解離させて溶出します。ウエスタンブロット法では、SDS電気泳動後のゲル内タンパク質をニトロセルロース膜やPVDF膜に転写し、抗体を用いた免疫化学的検出により特定タンパク質を同定します。ケミルミネッセンス法を用いることで、1バンドあたり10pg以下という高感度での検出が可能です。
参考)免疫沈降(IP)の原理と方法
組織免疫染色では、PAP(peroxidase-antiperoxidase)法などが用いられ、特定のタンパク質がどの組織に存在するかを観察できます。これらの抗原抗体反応を利用した技術は、基礎研究から臨床診断まで幅広く応用されており、免疫学や医療の発展に大きく貢献しています。抗原抗体反応の深い理解は、新しい診断法や治療法の開発、ワクチン設計の最適化につながる重要な知見となっています。
参考)新型コロナワクチンに誘導される記憶T細胞集団がワクチン接種ご…